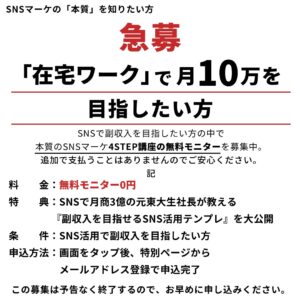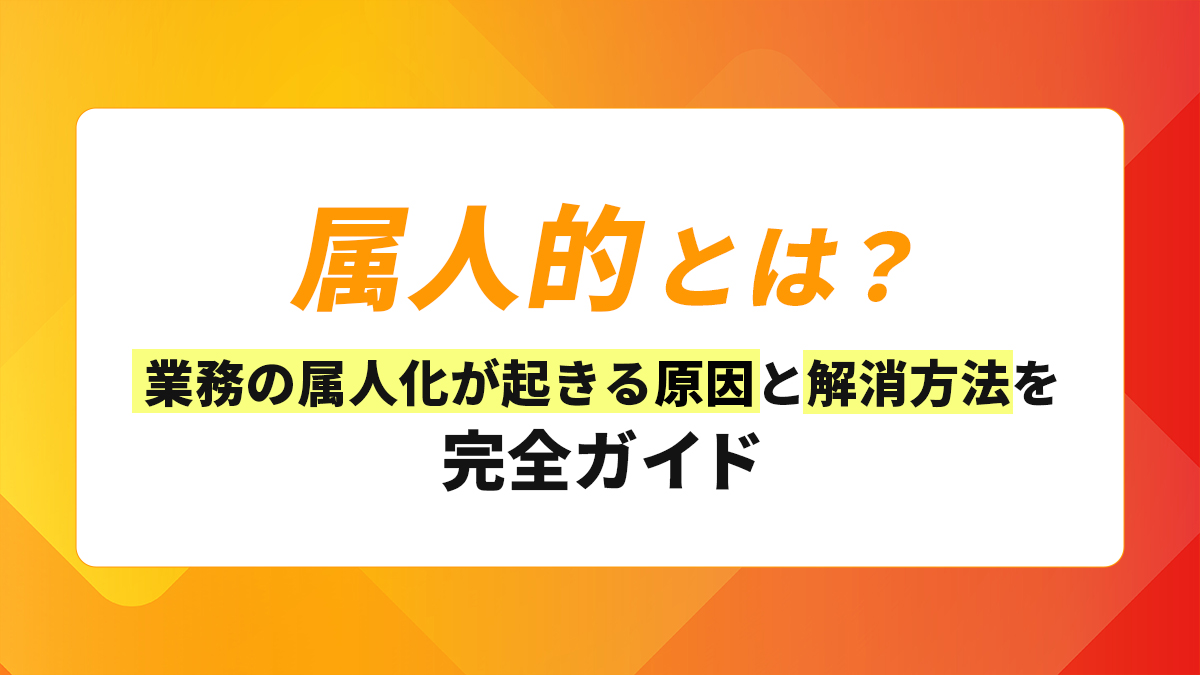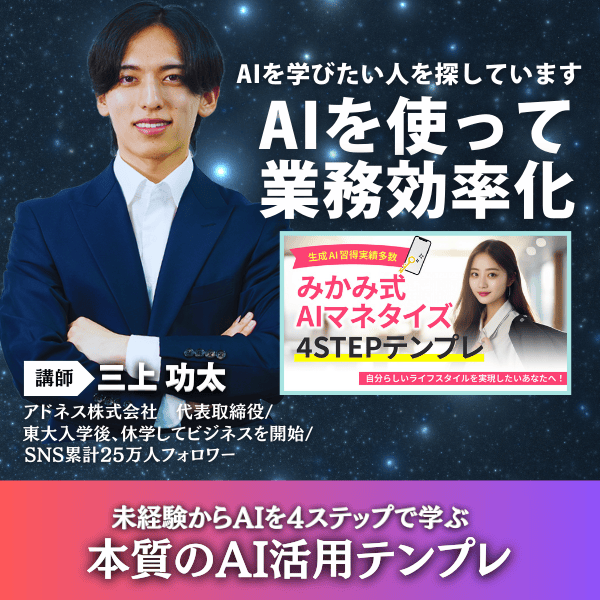属人的って、どういうこと?
はい、この記事では属人的という言葉について、定義や業務に起きる原因について詳しく解説していきます。
属人的とは?意味・定義とビジネス上の位置づけ
属人的の基本的な意味
「属人的(ぞくじんてき)」とは、業務や業績、知識・ノウハウなどが特定の個人に強く依存している状態を指します。これは、その人のスキルや経験、判断力がなければ成り立たないような状況であり、組織としての標準化や再現性が欠如していることが多いです。
属人的な業務は、担当者の裁量に任されているため柔軟性があり、スピード感のある対応が可能な一方で、担当者が不在になると業務が停止する、品質がばらつくといった問題が起こりがちです。
ポイント:属人的とは“再現性のない”個人依存型の業務運用のこと
「俗人的」との違い
ビジネスの現場では、「属人的」と「俗人的」が混同されることがよくあります。ここではこの2つの違いを明確にしておきましょう。
| 用語 | 意味 | 使用シーン |
|---|---|---|
| 属人的 | 個人のスキルや判断に依存していること | 業務プロセス、ノウハウ伝達 |
| 俗人的 | 世俗的・人間的な感情や嗜好に由来すること | 人柄、好み、個人的見解 |
属人的は組織運用上の課題に直結する用語であり、プロセス設計や業務改善の文脈で使われることが多いのに対し、俗人的は「俗人的な趣味」「俗人的な意見」など、もっと感情的・私的な意味合いで用いられます。
「属人的」と「標準化」の対比
「属人的」という言葉は、「標準化(マニュアル化)」と対比される概念として理解されることが一般的です。以下の比較表をご覧ください。
| 観点 | 属人的 | 標準化 |
|---|---|---|
| 再現性 | 担当者に依存し、再現が困難 | 誰がやっても同じ結果が出る |
| 知識管理 | 属人ノウハウが暗黙知化 | 明文化された共有ナレッジ |
| 業務速度 | 一部で高速化されるが属人に偏る | 安定したスピード維持が可能 |
| リスク | 担当者の不在=業務停止 | 引継ぎが容易でリスク分散可能 |
このように、属人的な業務は短期的には効率的に見える場合もありますが、組織全体としては属人性が高まると運営リスクが増加する傾向があります。
なぜ「属人的」が問題視されるのか
属人的な体制が生まれる背景には、組織の成長過程や人材配置、評価制度、経営スタイルなど複合的な要因が絡み合っています。特に中小企業やベンチャー企業などリソースが限られた環境では、自然発生的に属人的な業務運用が生まれがちです。
属人的=怠惰の産物ではなく、成長フェーズや環境制約の中で自然に発生する
しかし、そのまま放置すれば、事業継続性の低下、属人離職によるナレッジ損失、教育・育成の非効率性など、組織の持続可能性を脅かす深刻な課題へとつながります。
属人的業務チェックリスト
自社の業務が属人的かどうかを判断するためのチェックリストを紹介します。
- 特定の人しか操作できない業務ツールがある
- 引継ぎ資料が整備されていない
- 担当者が休むと業務が滞る
- 問い合わせ対応の判断基準が明文化されていない
- 「○○さんしか分からない」という会話が社内でよく聞かれる
2つ以上該当する場合は、属人的な状態にある可能性が高いといえます。
組織における属人的業務の見える化マトリクス
以下のマトリクス図は、業務の属人度と業務の重要度を2軸で分類したものです。
重要度↑
│
│ A(最優先対処)|属人度高 × 重要度高
│ ────────────
│ B(将来リスク)|属人度高 × 重要度低
│ ────────────
│ C(標準化維持)|属人度低 × 重要度高
│ ────────────
│ D(優先度低) |属人度低 × 重要度低
└─────────────────→ 属人度
このように、A領域(重要度が高く、属人度も高い)に該当する業務は、最優先で標準化・ドキュメント化が求められます。
次章では、「属人化によって起こる問題とリスク」について、より具体的かつ実践的に解説していきます。
属人化によって起こる問題とリスク
属人化は、特定の業務が一部の人に集中し、組織全体の健全な運営を妨げる大きな要因となります。ここでは属人化によって実際に起こる問題やリスクを、業務面・人材面・組織面の3方向から詳しく見ていきましょう。
業務面のリスク
業務の停滞・属人離職による業務停止
属人化の最大のリスクは、担当者が不在になったときに業務が回らなくなることです。例えば、1人の担当者しか理解していないシステム操作やクライアント対応があり、その人が急に休職・退職した場合、業務は完全に停止します。
実例:某中小企業でIT担当者が急遽退職。パスワード管理もすべて個人任せで、復旧に3週間かかった。
品質のバラつきと非効率なプロセス
属人的な業務は、個人の裁量に任されている分、判断や対応に一貫性がなくなり、顧客対応や成果物の品質にバラつきが出やすくなります。特に複数人で同じ業務を分担すべきケースでは、属人化は業務効率を大幅に下げる要因となります。
人材・組織面の課題
教育・引継ぎの困難
属人化された業務は、他人に引き継ぐのが非常に困難です。担当者が「自分でやった方が早い」と考える傾向が強く、情報の共有が進まないまま時間だけが経過します。その結果、後任者がゼロから業務を構築し直す必要があり、組織としての教育コストが膨らみます。
| 属人化が教育に及ぼす影響 |
|---|
| ナレッジが文書化されない |
| OJTの質が個人差に依存する |
| スキル継承が属人的に停滞する |
人材育成の停滞・リーダー不在の状態
属人的な体制では、若手や新入社員に業務が渡されず、スキルの習得機会が失われます。加えて、特定の人がいないと会議が進まない、判断ができない、といった状況が慢性化すると、リーダーが不在であるかのような“停滞感”が組織に蔓延します。
信頼・評価制度への悪影響
属人化が進むと、特定の人が必要以上に高く評価される一方で、他のメンバーの貢献が可視化されず、チームの公平性が崩れます。これによりモチベーションの低下や離職リスクが高まる可能性もあります。
例:「○○さんがいないと何もできない」=一見頼もしいが、裏返すと組織全体が弱体化している兆候
リスク可視化のフローチャート
以下に、属人化のリスクを段階的に判断するフローを示します:
[特定の人しかできない業務がある?]──Yes──→[業務の手順書・マニュアルはある?]
│
No
↓
[属人化による停止リスク:高]
このように、業務の標準化と文書化が行われていない状態で、特定の担当者のみに業務が集中している場合、属人化リスクは非常に高いといえます。
チェックリスト:あなたの組織は大丈夫?
以下に、属人化リスクが高まっている兆候をチェックリストとしてまとめました。
- その人が不在になると業務が止まる
- 引継ぎ資料が形骸化している
- 新人が独り立ちするのに半年以上かかる
- 「これ誰に聞けばいいの?」が頻出する
- 社内で“暗黙の了解”が多い
3つ以上該当すれば、組織として本格的に属人化対策が必要なタイミングです。
次章では、こうした属人化の根本的な原因を分析し、それにどう向き合うべきかを解説します。
属人化が生まれる原因を構造的に解説
属人化は偶然発生するものではなく、組織の構造・文化・運用設計などが複雑に絡み合って発生します。ここでは、属人化がどのような背景や要因で生じるのかを、構造的に分析していきます。
業務の複雑化とマニュアルの欠如
担当者の経験に依存した業務設計
属人化の最も一般的な要因は、業務の手順や判断が属人の経験値や直感に依存している点にあります。業務が高度にカスタマイズされていたり、例外処理が多かったりすると、標準化が困難になり、結果として特定の人しか対応できない体制が生まれます。
ケース:特定の営業担当が持つ顧客情報や交渉ノウハウが口頭伝承のみで継承されず、新人は何も分からず引き継げない。
文書化コストの後回し
忙しさや人手不足を理由に、マニュアル化が後回しにされることも属人化の原因です。特に創業間もない企業やベンチャーなどでは、「まずやってみる」文化が先行し、文書化が後手に回る傾向があります。
情報共有の不全と縦割り体質
部門間・チーム間の連携不足
部門ごとに情報の流れが断絶しており、全体最適よりも部分最適が優先される体制では、情報が属人的に閉じてしまう傾向が強まります。特に、業務報告や会議体が形式的な場合、現場の知識が他の人に伝わらず、属人化を助長します。
| 属人化を助長する組織の特徴 |
|---|
| 情報共有が属人の善意に依存している |
| 成果報告が個人に閉じている |
| 他部門との交流がほとんどない |
サイロ化(情報の孤島化)
業務が部門内で完結しすぎると、他のメンバーが業務内容を知る機会が減少します。このような“情報の孤島”は属人化の温床となり、最終的には業務継続性を損なう原因となります。
組織文化・経営スタンスの影響
「任せきり」マネジメントの常態化
属人化が起きやすい組織では、「○○さんに任せておけば安心」という文化が根付いている場合が多いです。これは信頼の裏返しでもありますが、業務の属人依存が進行しやすい状態を放置しているともいえます。
評価制度の偏り
「成果さえ出せばOK」という成果主義が強すぎる場合、その成果がどのようなプロセスで生まれたのかが軽視され、結果的に属人的なやり方が常態化してしまうケースもあります。
スキル偏重採用と育成戦略の欠如
属人的な組織では、優秀な個人を“即戦力”として採用し、育成や仕組み整備を怠りがちです。その結果、個人技頼みの体制が進み、新人や中堅層が育たないという悪循環が生まれます。
「属人的」な強者は組織の武器にもなるが、育成の観点を欠くと、組織全体が脆弱になる。
| 属人化を生む人材管理の誤り |
|---|
| 育成よりも採用に偏る戦略 |
| OJTが属人的に行われる |
| ナレッジ共有が文化として根付いていない |
属人化要因マトリクス(内部要因×外部要因)
| 視点 | 内部要因 | 外部要因 |
|---|---|---|
| 業務設計 | マニュアル未整備/例外処理多発 | 顧客要求の多様性 |
| 情報管理 | 情報共有不全/属人知識のブラックボックス化 | 部門間調整の機会不足 |
| 組織文化 | 任せきりマネジメント/属人頼みの文化 | 競争・成果重視の市場圧力 |
このように、属人化は単なる「担当者の怠慢」や「運用ミス」ではなく、組織構造・文化・外部環境の複合的な結果として起こる現象です。
次章では、属人化をどのように解消・予防すればよいのか、具体的な手段を体系的に紹介します。
属人化を解消・予防する具体的な対策
属人化は自然に解消されるものではありません。明確な意図と仕組みに基づいた対策が不可欠です。この章では、属人化を解消・予防するための実践的な手法を「業務標準化」「ナレッジ共有」「組織文化改革」の3つの柱で具体的に紹介します。
業務の標準化と仕組み化
マニュアル・チェックリストの整備
業務標準化の基本は、手順の明文化です。業務マニュアルやチェックリストを用意することで、誰でも同じ業務が再現できるようになります。ポイントは、専門用語を避けて“新人が読んでも分かる”表現にすることです。
ヒント:1業務=1ファイルで完結、画像や動画で補足するとなお効果的
業務プロセスの可視化とKPI設計
業務の流れをフローチャートやプロセスマップで可視化することで、属人化の温床となる“見えない工程”を排除します。同時に、業務ごとにKPI(重要業績評価指標)を設定し、成果とプロセスの両方を管理することで業務の透明性が高まります。
| 可視化ツール例 | 活用ポイント |
|---|---|
| フローチャート | 工程の分岐や判断条件を見える化 |
| ガントチャート | タスクの進行状況を全員が把握可能に |
| 業務別KPI表 | 定量指標で成果と標準を明示 |
ナレッジ共有と属人知識のオープン化
情報共有ツールの導入
ナレッジを“属人から組織へ”移行させるためには、情報共有の仕組みが必須です。社内Wikiやナレッジベース、Notion・Confluence・Backlogなどのツールを活用し、誰でもアクセスできる場所にナレッジを集約します。
ポイント:属人ノウハウを“当人がいなくても伝わる状態”に変換する
勉強会・クロストレーニングの導入
社内勉強会を定期的に開催することで、ナレッジの循環が促進されます。また、部署を超えたクロストレーニング(交差教育)を取り入れることで、他業務への理解が深まり、業務の冗長性(リダンダンシー)が高まります。
| ナレッジ共有手法 | 特徴・利点 |
|---|---|
| 勉強会 | 特定テーマに集中、質疑応答で定着率UP |
| ローテーション制度 | 複数業務を経験させ属人回避 |
| メンター制度 | 継承者を明確化、教育スピード向上 |
組織文化の改革と人材設計
心理的安全性と情報の開示文化
情報共有が進まない背景には、「発言しづらい」「聞くと無知と思われる」といった心理的障壁があります。属人化を防ぐには、誰もが自由に質問・提案できる空気=心理的安全性を醸成する必要があります。
役割の多様化と人材流動性の確保
「この人しかできない」という状態を打破するには、業務をチームで持つ設計が重要です。複数人で分担・バックアップ体制を築き、「属人的なスペシャリスト」ではなく「共有可能なスキルセット」を重視する人材設計が求められます。
| 組織文化施策 | 効果 |
|---|---|
| 1on1ミーティング | 不安・課題を可視化しやすくなる |
| 情報開示のルール化 | 知識・情報を貯めずに流通させる文化を醸成 |
| 評価制度の見直し | 個人ではなく“仕組み化”に貢献した人を評価 |
属人化対策ロードマップ(6ステップ)
- 属人化の現状把握(業務棚卸・属人度評価)
- 優先業務の可視化(A領域の洗い出し)
- ドキュメント整備と標準化
- ナレッジ共有ツールの導入・教育体制整備
- クロストレーニングと役割の多様化
- 組織文化と評価制度の再設計
この6ステップに従えば、属人化の“解消”だけでなく“再発防止”も見込めます。
次章では、属人化の否定一辺倒ではなく、「属人的であること」そのもののメリットと活かし方について掘り下げていきます。
属人化のメリットと活かし方
属人化は一概に「悪」とされがちですが、必ずしもそうとは限りません。個人に依存するからこそ得られる柔軟性やスピード感、専門性が業務効率や顧客満足度を高めるケースもあります。この章では、「属人的であること」のポジティブな側面に焦点を当て、そのメリットと活かし方を紹介します。
専門性の発揮と迅速な意思決定
属人化がもたらす最大の利点は、特定分野における圧倒的な専門性と、それに基づく迅速な判断力です。例えば、長年同じクライアントを担当してきた営業パーソンであれば、マニュアルでは拾えない細かな要望に即応できるため、満足度が高まりやすくなります。
ケース:熟練エンジニアが独自に調整した運用設計により、システム停止リスクを大幅低減。
| 属人性が有効な場面 | 理由 |
|---|---|
| クライアント対応 | 信頼関係・交渉スキルが個人に依存して成立する場面が多い |
| 緊急時の判断 | 経験に基づいた即断即決が可能になる |
| 特殊技術・スキル | 高度な専門職はマニュアル化に限界がある |
顧客対応の柔軟性と信頼関係の構築
属人性があることで、顧客は「この人に任せれば大丈夫」という安心感を抱くようになります。特にBtoB取引では担当者との信頼関係が契約継続のカギとなるため、属人的要素が信頼構築に寄与する側面は無視できません。
注意点:この信頼関係が“個人”に依存しすぎると、退職時のリスクが高くなるため、情報や関係性の共有が並行して必要。
モチベーション向上と主体性の発揮
「この仕事は自分にしかできない」という責任感は、担当者のモチベーションを高める要因になります。属人的な業務には裁量が大きく、自律的に動ける自由度があるため、やりがいを感じやすい構造です。
| 属人的な仕事がモチベーションに与える影響 |
|---|
| 判断権限があることで仕事の“意味”を実感できる |
| 顧客や社内からの信頼により承認欲求が満たされる |
| 成果が可視化されやすく達成感を得やすい |
「良い属人化」と「悪い属人化」の違い
属人化には“良し悪し”の線引きがあります。以下の比較表をご覧ください。
| 区分 | 内容 | 組織にとっての影響 |
|---|---|---|
| 良い属人化 | 専門性・柔軟性を発揮し、組織に還元する | 業務効率や満足度が向上、属人知識も共有可能 |
| 悪い属人化 | 情報の囲い込み、独断的な運用 | 業務停滞・不透明化・リスク集中 |
判断基準は「そのノウハウ・判断が、他者に共有可能かどうか」。
属人性を活かすための条件
ナレッジの還元構造を整える
属人的な強みは“再現可能な形で”組織に還元されてこそ価値を持ちます。そのためには、属人知識をドキュメント化・仕組み化し、「再利用可能な状態」にするナレッジフロー設計が必要です。
ヒント:「属人→標準→育成→属人→再標準化」のサイクルを回す
一時的な属人性の活用を前提とする
「最初は属人でもよいが、徐々に共有・継承していく」ことを前提にすれば、属人的な働き方も成長と仕組み化の過程としてポジティブに捉えることができます。
属人化メリット活用フロー
[専門的ノウハウの集中] → [迅速な対応力と信頼獲得] → [チームへの還元設計] → [組織力として定着]
この流れを意識することで、属人性は「危機」ではなく「競争力」へと転換可能です。
次章では、実際に属人化対策や活用に成功している企業の事例と、そのベストプラクティスを紹介します。
属人化に向き合う企業の実践例とベストプラクティス
理論だけでは属人化の解消は進みません。実際に取り組んで成果を出している企業の事例から学ぶことで、自社に合った対策や応用のヒントが得られます。この章では、部門別の属人化事例と、その克服や活用に成功した企業の実践例を紹介します。
部門別:よくある属人化の実例
| 部門 | 属人化が起きやすいポイント | 影響 |
|---|---|---|
| 営業 | 顧客対応・関係構築・価格交渉 | 顧客情報の属人管理、引継ぎ困難 |
| 開発 | 特定領域の技術・設計知識 | コードが読めない、障害対応遅延 |
| 人事 | 採用・労務・制度運用ノウハウ | 担当変更で業務の質低下 |
| 情報システム | インフラ構成・アクセス管理 | トラブル発生時の属人対応依存 |
| カスタマーサポート | FAQ対応・顧客対応トーン | 対応のばらつき・再現性低下 |
実践事例①:営業部門の属人化を解消したSaaS企業
課題:
長年同じ担当が持つ大口顧客が多数。退職後の売上減少が課題。
対策:
- Salesforce上で顧客対応履歴を全記録
- 交渉プロセスやメール文面もテンプレ化
- クロスセル・アップセル情報を社内Wikiで共有
結果:
売上の変動が抑えられ、後任の育成が加速。
チーム単位での営業活動へ移行。
実践事例②:IT企業の開発部門で属人コードを撲滅
課題:
あるシステムの中核部分が1人しかメンテナンスできない状態。
対策:
- ペアプログラミング導入
- GitHubで設計意図もコードコメントとして残す
- 技術ドキュメントをNotionで一元管理
結果:
属人コードが可視化・継承され、他のメンバーでも保守が可能に。
バグ対応のスピードが30%向上。
実践事例③:人事制度の属人運用から仕組み化へ(中堅メーカー)
課題:
採用や評価がベテラン担当の経験則に依存し、新任担当が育たない。
対策:
- 評価制度・面接フローを全てフローチャート化
- 定期レビューとフィードバック制度を標準実装
- OJTで業務を録画・マニュアル化
結果:
担当者交代時の混乱が激減。
育成サイクルが明確になり、新人でも安定運用可能に。
ベストプラクティスまとめ
| 対策カテゴリ | 具体策 | ポイント |
|---|---|---|
| 情報の可視化 | 業務フロー・履歴記録・テンプレート | 誰でも経緯が分かる状態を作る |
| 継承と教育 | ペア作業・OJT・マニュアル | “暗黙知→形式知”への変換を重視 |
| 共有文化 | 社内Wiki・勉強会・1on1 | 情報が滞らない風土を醸成 |
属人化は完全になくすことはできませんが、構造と文化によってコントロールすることは可能です。
次章では、この記事全体の総まとめとして、「属人的であることの本質」とどう向き合うべきかを整理します。
まとめ|属人的であることの本質と向き合い方
属人的という言葉には、ネガティブなイメージがつきまといがちですが、本質を見誤らないことが重要です。本記事で解説してきたように、属人化には「リスク」だけでなく「可能性」も含まれています。ここでは、属人性と組織の関係性を再定義し、現代組織における向き合い方をまとめます。
属人的=“悪”という先入観を捨てる
属人的な体制が問題になるのは、それが不透明・再現不可・非共有な状態に陥ったときです。逆に言えば、属人性が発揮されつつも、それを組織全体の資産として蓄積・継承できているのであれば、それは「強み」に転換できます。
| 状態 | 属人的なまま | 属人的だが仕組み化済み |
|---|---|---|
| 評価 | 個人のスキルに依存 | 組織的成果に変換可能 |
| 継承 | 引継ぎ困難 | 後進への育成パスがある |
| リスク | 休職・退職で業務停止 | 業務継続性を確保 |
属人化対策は「組織成熟度」のバロメーター
属人化対策の有無やレベルは、組織の成熟度や戦略性を示す指標でもあります。創業期や少人数フェーズでは属人的体制が避けられないとしても、成長とともにそれを“仕組み”に昇華できるかどうかが、次のステージへの分岐点となります。
属人化から脱却できる組織=再現性のある強い組織
成熟度別:属人化マネジメントの目安
| 成長段階 | 状態 | 重点対策 |
|---|---|---|
| 創業期 | 少人数・役割不明確 | 属人性を活かしながらドキュメントを蓄積 |
| 拡大期 | 中堅社員が業務を独占 | 標準化・ナレッジ共有体制の構築 |
| 成熟期 | 組織の最適化フェーズ | 再発防止と属人性活用のバランス設計 |
属人的であることを、武器にする
「属人的であること」は、創造性や判断力、責任感の象徴でもあります。重要なのは、それを“閉じた知”にせず、開かれた知識として共有・再利用できる仕組みを整えることです。
- 属人知識 → 文書化・形式知へ
- 専門スキル → OJTや教育で伝承
- 個人判断 → 判断基準を明文化
このような形で属人性を「知的資産」として活かすことで、個人の力を組織の力に昇華することが可能になります。
最後に:属人性とともに成長する組織へ
属人的な体制から完全に脱却するのではなく、属人性を受け入れ、活かしながら、コントロールする組織こそが、変化の激しい現代において柔軟かつ持続的に成長できる組織です。
属人化を「管理する力」は、イコール「組織をデザインする力」である──。
これが、本記事を通じてお伝えしたかった結論です。